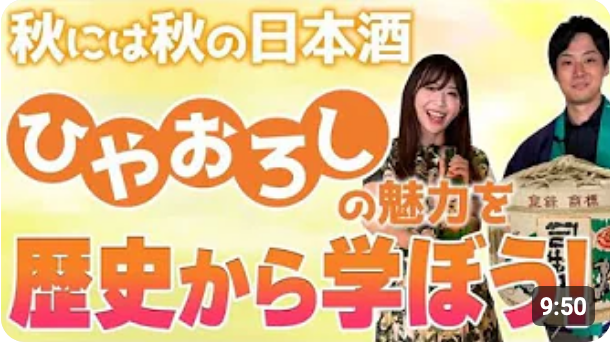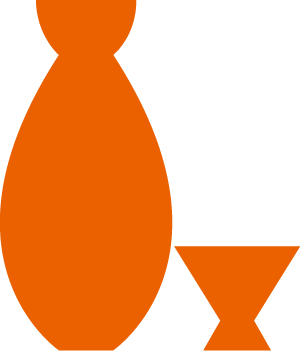|
秋の酒 豊穣の秋に円熟の味わいを実りの秋──9月から木枯らしが吹く初冬にかけて、 実りの秋──9月から木枯らしが吹く初冬にかけて、ひと夏を酒蔵で過ごした秋の限定酒「ひやおろし」の出荷が始まります。秋に目覚めたお酒は穏やかで落ち着いた香り。その味わいは、秋の深まりとともにまろやかさと旨味を増し、次々に登場する魅力的な秋冬の味覚と引き立て合います。日本の食と酒が最高の状態で出会う季節の始まりです。 「ひやおろし」はどんなお酒?「ひやおろし」の楽しみ方秋には秋の日本酒『ひやおろしの魅力』を歴史から学ぼう!on youtube(2024)秋酒「ひやおろし」。季節とともに移ろう日本酒の魅力と、秋酒ならではの美味しさを、歴史を紐解きながらご紹介。 「ひやおろし」はどんなお酒?「ひやおろし」とは
「ひやおろし」とは、江戸の昔、冬にしぼられた新酒が劣化しないよう春先に火入れ(加熱殺菌)した上で大桶に貯蔵し、ひと夏を超して気温が下がり、外気と貯蔵庫の中の温度が同じくらいになる頃、2度目の加熱殺菌をしない「冷や」のまま、大桶から樽に「卸(おろ)して」出荷したことからこう呼ばれ、秋の酒として珍重されてきました。 ときは移って現在、日本名門酒会の「ひやおろし」も、春先に一度だけ加熱殺菌し、秋まで熟成させて、出荷前の2度目の火入れをせずに出荷されます。貯蔵の形こそ、タンクや瓶に変わりましたが、その本質は昔と変わりません。 暑い夏の間をひんやりとした蔵で眠ってすごして熟成を深め、秋の到来とともに目覚める「ひやおろし」。豊穣の秋にふさわしい、穏やかで落ち着いた香り、なめらかな口あたり、まろやかな適熟の味わいが魅力のお酒です。 一度火入れのまろやかな味わい一般的な日本酒では、発酵を止め、風味を悪くする微生物を殺菌し、香味を保つなど保存性を高めるため、「火入れ」という低温加熱殺菌を行います。通常は出荷までに2度──貯蔵する前に1度、さらに出荷直前に1度──行われます。日本名門酒会の「ひやおろし」は、春先に一度だけ「火入れ」し、秋まで熟成させ、出荷する際の2度目の「火入れ」をせずに出荷されます。 1度目の貯蔵前に「火入れ」するのは、安定して熟成させるため。冷蔵技術が発達した現在では、「火入れ」をしない生のまま低温貯蔵することも可能ですが、生酒には米麴由来の酵素が残っているため、普通の冷蔵庫程度の低温貯蔵では、酒質が変化してしまいます。かといって、貯蔵温度が低く過ぎると熟成が進まず、秋口に熟成の旨みは出てきません。 2度目の「火入れ」をしないのは、蔵元で適熟させたお酒の繊細な香りや味わいのバランスを加熱によって壊すことなくお届けするため。加熱により、香りが変化したり、熟成によって馴染んだ味わいが元に戻ってしまうことがありますが、それを避けるためです。 味わいの成分がよく溶け合ったまろやかな味わい、それが日本名門酒会の「ひやおろし」です。 季節の移ろいとともに深まる味わい
世界中のお酒の中で、四季の移ろいを楽しめる唯一のお酒が、日本酒です。寒い冬に造られた日本酒は1年をかけて熟成していきますが、特に暑い盛りの夏を越えると、大変身。涼しい蔵の中で眠るお酒は熟成が進み、味わいの成分が馴染んで、旨みが増しまろみを帯びてバランスのよい状態に。 その熟成の旨みを、もっともよく伝えてくれるのが、この「ひやおろし」です。穏やかで落ち着いた香りと、まろやかな旨味を特徴とする「ひやおろし」は、旨みののった秋の味覚とお互いを引き立て合う抜群の相性の相性を発揮します。サンマや戻りガツオなど脂ののった海の幸、キノコやギンナンなど香り高い山の幸はもちろん、熟した柿や梨など秋の果物ともよく合います。 深まる秋 深まる旨味「ひやおろし」は秋の間にも、瓶の中でゆるやかに熟成をすすめ、刻々と味わいを深めていきます。暑さの残る9月にはフレッシュ感も残す味わいのお酒が、10月、11月になるとまろやかさと旨味を増し、数ヶ月でここまで変わるのか、と驚くほどの変身を遂げることも。同じお酒を月を追って飲むのも楽しいかもしれません。 各蔵の個性あふれる秋味蔵元によって、その個性はさまざま。地域の自然や食文化を映し、「ひやおろし」ならではの美味しさを追求した造り手の情熱やこだわりが結晶した個性あふれる味わいを、この秋もお楽しみください。 「ひやおろし」の楽しみ方飲み方で変わる、万能な表情冷やしたり温めたりソーダで割ったり。楽しみ方は自由自在。 冷やして・常温で・温めて幅広い温度帯で楽しめるのが日本酒の魅力ですが、「ひやおろし」もまたしかり。冷やして爽やかに、常温でまろやかさをじっくり、温めてより複雑な表情を見せるものも。気温が急速に落ちていく秋、その日の気温や気分、お酒やお料理の特質に合わせて、様々にお楽しみいただけます。 SAKEハイのススメ
日本酒を炭酸水で割って楽しむ日本酒ハイボール、通称「SAKEハイ」は、軽快で飲みやすく爽快!と最近話題の飲み方です。「ひやおろし」の豊かな風味を活かしたSAKEハイは、暑さがまだ残る秋口におすすめ。 美味しい「SAKEハイ」の作り方1. 日本酒と炭酸はよく冷やす 
2. 日本酒と炭酸は1:1の割合で 
3. 上下に軽くステアして楽しむ 
ちょっとアレンジ
秋の味覚を引き立てる「最高の食中酒」熟成によって生まれた「ひやおろし」の旨味やコクは、秋に旬の食材と抜群の相性。秋の深まりとともに、たとえば魚なら「サンマ」「戻りガツオ」「寒ブリ」などは脂がのってより濃厚な味わいになり、茸や果実などの食材も豊富になります。それと呼応するかのように、「ひやおろし」もまろやかさを増し旨味が凝縮されていき、秋の味覚を最高に引き立ててくれます。旬の味覚と「ひやおろし」を合わせ、秋の風情をお楽しみください。 白露の頃〜 "走り"の味わい
夏を越したばかりの「ひやおろし」は、苦味や渋みがやわらぎ、粗さもすっかりとれ、軽快さとまろやかさをあわせもった、まさに "走り"の味わい。脂ののったサンマなど、出始めの秋の食材と合わせれば、いち早く秋の訪れを感じることができます。 白露(はくろ)9月7日しらつゆが草に宿る頃。朝夕に肌寒さを感じ始めます。旬の食材:さんま・椎茸・栗
秋分・寒露の頃〜 "調熟"の味わい
日も短くなり、秋も深まってくる秋分から寒露の頃になると、「ひやおろし」も味ノリして香味のバランスもますます整い、"調熟"の味わいに。香り高いマツタケなどとの相性も抜群。これぞ秋!という美味しさを堪能できます。 秋分(しゅうぶん)9月23日秋の彼岸の中日。昼夜の長さが同じに。旬の食材:銀杏・里芋・かつお
寒露(かんろ)10月8日露が冷たく感じられてくる頃。五穀の収穫もたけなわを迎えます。旬の食材:松茸・ししゃも・柿
霜降の頃〜 "熟れきった豊醇さ"
山々が紅葉し始める霜降の頃、「ひやおろし」はまろやかさと旨味をさらに増し、"熟れきった豊醇さ"と呼ぶにふさわしい風味に。しっかりした旨味のある素材を、味噌・醤油をきかせて調理した料理とよく合います。お燗にしても美味しく、朝晩冷え込み始めるこの頃には、ほどよいぬる燗もおすすめです。 霜降(そうこう)10月23日早朝に霜が降りる頃。山々の葉が色づき始めます。旬の食材:さけ・いくら・山芋
立冬・小雪の頃〜 "完熟の旨味"
立冬の頃までじっくり熟成し豊かな旨味がさらに深まった "完熟の味わい" は、お燗酒もおすすめ。あつあつのおでんや鍋物との組み合わせは、冷え込む夜に至福の味わいです。 立冬(りっとう)11月7日冬の気配が感じられる頃。木枯らしが吹き始めます。旬の食材:さば・なめこ・毛蟹
小雪(しょうせつ)11月22日山に初雪が舞い始める頃。寒さの強まる冬の入り口です。旬の食材:ふぐ・白菜・りんご
そして「新酒しぼりたて」へ……
11月後半からは各地の酒蔵での酒造りも本格化し、新酒が次々と産声を上げ、日本酒の新たな一年が始まります。「寒おろし」などまろやかに熟成したお酒とフレッシュな「新酒しぼりたて」、2つの美味しさを同時に楽しめるのは、この時期ならでは。 大雪(たいせつ)12月7日山々には雪が降り積もる頃。本格的な冬の到来です。旬の食材:ぶり・大根・牡蠣
冬至(とうじ)12月22日一年で最も昼が短く夜が長い日。旬の食材:ズワイガニ・百合根・たら
|
| カテゴリに戻る | カテゴリの一覧に戻る |